「社長を辞めたい」と思っているそこのあなたへ。社長も、いつでも自分のタイミングで辞任することができると知っていますか?
社員のようにいつでも辞めることはできますが、社長の辞任に当たっては手続きがなかなか面倒です。
今回は社長が辞任した際にどんな手続きが必要なのか、辞任するに当たり事前に確認しておくべき項目などを紹介していきます。
社長が辞任する際に必要な手続き
ここからは、社長が辞任をするにあたり必要な手続きを確認していきましょう。
- 辞任の意思表示
- 登記申請書類の作成
- 変更登記申請を行う
辞任の意思表示
社長(代表取締役)や取締役は、会社とは委任関係にあるため、自分の望んだタイミングで辞任することができます。
辞任することの意思を表示するために、辞任届を用意しましょう。口頭でも大丈夫ですが記録として残らないため、後々トラブルになることもありますので、書面を用意するのがベターです。

登記申請書類の作成
社長(代表取締役)や取締役が辞任した場合、法務局へ変更登記申請を行う必要がありますので、そのための登記申請書類を作成しましょう。

変更登記申請を行う
社長(代表取締役)や取締役の場合、氏名は登記事項となっているため会社の登記簿謄本に氏名が記載されている状況です。
役員以上の人物が辞任などをした場合、役員変更の登記申請を行う必要があります。変更登記は、辞任後2週間以内に法務局へ申請する必要がありますので、書類の準備などは迅速に行いましょう。
変更登記申請は社長が辞任してから2週間以内に手続きを!
社長(代表取締役)や取締役が辞任した場合、辞任したその日から2週間以内に変更登記申請を行いましょう。役員の人数は定款で定められているので、人数を欠いてはいけません。
社長(代表取締役)や取締役が辞任をしたら、実質役員の人数が欠けている状況ですから、迅速に後任を決める必要があります。
原則として変更登記申請の期間は、辞任したその日から2週間となっていますが、2週間を過ぎたとしても変更登記申請は受け付けてもらうことができます。
ただし、2週間をあまりにも過ぎてしまうと、追加料金を徴収される可能性もあるので注意してください。
第三者に対して「辞任した」と主張できない
先ほどから紹介している「変更登記申請」に関してですが、変更登記申請をしていなければ、第三者に対して「自分はこの会社の代表取締役を辞任した」と話しても効力が発揮されません。
例えば他社からの引き抜きがあった場合、引き抜かれる会社側に「この会社の取締役を辞任した」と伝えるとは思いますが、変更登記申請が完了していなければ、効力を発揮しません。
効力を発揮していない段階で「辞任した」ことを外部に公表してしまうと、どんなトラブルに巻き込まれるかわからないので注意してください。しっかりと辞任が決定するまでは外部に漏らさないほうがいいでしょう。
社長辞任の手続きに当たり、取締役会設置の有無を確認しよう
 出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%97-%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0-1245776/
出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%97-%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0-1245776/社長が辞任するに当たり、取締役会を設置しているかどうかを確認しましょう。そもそも「社長=代表取締役」は、取締役としての役職も兼ねています。
しかし取締役会が設置されているかどうかで、代表取締役だけを辞任できたり、両方を辞任しなければならなかったりと、辞任の手続きが少し異なります。
取締役会を設置している会社の場合
取締役会を設置している会社の場合、代表取締役の地位のみの辞任が可能です。取締役としての地位は残しておけると言うことです。
代表取締役のみを辞任する場合には、辞任届だけで辞任が成立します。
取締役会を設置していない会社の場合
取締役会を設置していない会社の場合、定款に何が書かれているかで辞任方法や用意すべき書類が異なります。
定款の内容によって、辞任の手続きや用意すべき書類はどのように変わるのか、次の章から紹介していきます。
社長辞任の手続きに当たり、定款を確認しよう
社長の辞任に当たり、定款に記載されている内容次第で、辞任方法や用意すべき書類も変わってしまいますので、必ずチェックしておきましょう。
代表取締役の氏名が記載されている場合
定款に、代表取締役の氏名が記載されている場合には、代表取締役と取締役の地位は一本化している、と見なされます。
そして、代表取締役の辞任の意思だけでは代表取締役の地位を辞任することはできません。定款に書かれている内容を変更する必要があるため、株主総会の特別決議を行います。
定款を変更すれば、代表取締役の地位を辞任することができます。
「代表取締役は取締役の互選で選定する」と記載されている場合
定款に「代表取締役は取締役の互選で選定する」と記載されている場合には、代表取締役の地位のみの辞任が可能です。
退任登記に当たり、必要となる書類は代表取締役の辞任届と定款です。定款は、「互選で選定する」と言う規定が記載されていることを示すために必要となります。
「代表取締役は株主総会の決議で選定する」と記載されている場合
定款に「代表取締役は株主総会の決議で選定する」と記載されている場合には、代表取締役の意思表示だけでの辞任はできません。
この場合も、代表取締役と取締役の地位は一本化している、と見なされるため、株主総会での代表取締役の辞任について承認決議が必要となります。
社長の選定方法を確認しよう
社長の選定方法に関しても、選定方法や決まりについて確認をしておきましょう。
- 取締役会の決議
- 株主総会の決議
取締役会を設置していない会社の場合には、基本的に代表取締役と取締役の地位は一本化されているため、取締役として選ばれた時点で代表取締役として選任したことにもなります。
しかしながら、下記の方法によって取締役の中から、特定の人物を代表取締役として選定することもできます。
- 取締役の互選
- 株主総会の決議
- 定款で定める
- 代表取締役の選定方法を定めない
取締役の互選
取締役の中から、互選をすることによって代表取締役を選定します。取締役の互選は、取締役の過半数の賛成が必要となるので注意してください。
定款において代表取締役の選定方法を「取締役の互選」と定めている会社の場合は、株主総会で代表取締役を選定することはできません。
株主総会の決議
定款に、株主総会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定する、と定めておくこともできます。
その場合は、株主総会の決議によって代表取締役を選定することになるため、辞任するときは自分自身の意思だけでは辞任することができず、株主総会の決議が必要です。
定款で定める
定款で直接代表取締役を定めておくこともできます。(氏名を記載します。)
取締役に選定された時点で、誰もが代表取締役になる権利を保有していることになりますが、定款で代表取締役とされた人物以外の取締役は、代表取締役としての権利・権限はありません。
代表取締役の選定方法を定めない
代表取締役の選定方法を定めないことも、代表取締役選定方法の1つと言えます。
先ほども記しましたが、取締役は誰もが代表取締役になる権利を保有しています。ですから、「代表取締役の選定方法を定めない」とすることで、取締役に選ばれた全員が代表取締役となります。
互選とは?
先ほどから何回か登場している「互選」と言う言葉について説明しておきます。互選と言うのは、「お互いに選挙をして選ぶこと」を意味します。
先ほど「代表取締役は取締役の互選で選定する」と言う話をしたのですが、これは代表取締役を、取締役がお互いに選挙をして選定すると言う意味です。
互選は、基本的に過半数以上の取締役の票が必要となります。例えば、5人の取締役がいて、互選によって代表取締役を選定するという場合には、3人以上の票が集まらなければ代表取締役として選定できません。
互選と言う言葉はよく登場するので、覚えておくようにしましょう。
社長辞任の手続きに当たり、事前に後任を決めよう
社長の辞任手続きをするに当たり、事前に後任を決めておきましょう。定款に記載されている取締役の人数を割ることは、会社の運営が停滞するなどの理由から認められていません。
例えば、代表取締役や取締役を辞任した場合、後任が決まっていなければ後任が決まるまで、代表取締役や取締役の権利義務を有することになります。
辞任届を出したとしても、事実上は辞任が完了していないと言うことにもなります。後任が決まっていなければ、退任登記もできません。
基本的に「この時期に辞任をしたいから後任を決めておこう」と、前もって準備するケースはまずないとは思いますが、辞任をする場合にはある程度後任の目星をつけておいたほうがいいでしょう。
社長が辞任する際に損害賠償の支払い手続きが起こる場合も
社長が辞任するにあたり、実は損害賠償の支払い手続きが必要となる場合があります。会社にとって「不利な時期」に辞任を申し出た場合、会社の損害を賠償しなければならないという決まりです。
なお、取締役にとってやむを得ない理由がある時には、損害賠償責任はありません。やむを得ない理由は、社長や取締役として仕事をしていて、重大な被害を被る可能性がある場合などとなっています。
場合によって損害賠償責任が発生するかどうかは異なるので、「損害賠償責任が発生するときもあるんだな」程度に覚えておいてください。
まとめ
社長が辞任をした場合の手続きについて紹介をしてきました。社長はなかなか辞任できないものだと思っている人もいるかもしれませんが、いつでも辞任を表明することはできます。
ただ、辞任をした後の手続きは社員が辞任した場合とは違うため、きちんとした知識を備えておきましょう。
また、一概に社長を辞めると言っても、取締役会を設置しているかどうかや、定款に記載されている代表取締役の選定方法などで、手続きが変わってきます。
社長(代表取締役)の辞任が身近で起きた経験がない人の方が少ないと思いますので、わからないポイントがあれば、再度この記事を読み直してみてください。

本ページでは「とにかく安い値段で退職代行を使いたい」という方に向けて、数ある退職代行サービスの中から「依頼料の安い退職代行」をランキング形式でご紹介します。
とはいえ、いくら料金が安くても、退職できるとは限らないサービスは使いたくないですよね。
料金の安さはもちろんのこと、最低限しっかりと退職が実現できるだけの「サービスの質」も考慮したランキングとなっています。
「退職のために大きなお金は払いたくない。でも、しっかり退職までサポートしてもらえる退職代行サービスを利用したい」という方は、ぜひここで紹介している退職代行の利用を検討してみてください。
※以下に掲載する料金は全て「税込価格」です。
【格安で依頼可能】退職代行ランキング Top5
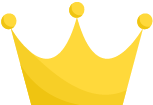 【1位】キャリアサンライズ
【1位】キャリアサンライズ
☆最も安い退職代行サービス

キャリアサンライズは、業界最安値でサービスを提供している退職代行サービスです。
退職代行の相場が3〜5万円なので、「他サービスの約半額」の料金で退職代行を依頼できるということになります。
ただし、この価格は「退職代行」に特化しているからこそできるものであり、残業代や有給に関する交渉などはサポート外となっています。
そのため、特に交渉をする予定はなく、ともかく安い料金で一刻も早く退職したいという方にお勧めのサービスです。
| 料金 | 15,000円 |
| 特徴 | ・業界最安値の退職代行サービス ・転職サポートのサービスもあり(別料金 |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 不可 |
| こんな人におすすめ | ・とにかく低価格で退職代行を依頼したい人 ・残業代などの交渉は考えていない人 |
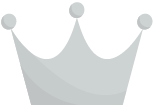 【2位】わたしNEXT
【2位】わたしNEXT
☆女性で退職代行の利用を考えている方の第一候補

わたしNEXTは、女性をメインターゲットとした退職代行サービスです。(男性も利用可能。)
日本退職代行協会の特急認定を受けてるほか、退職率100%、顧客満足度98.7%と「安心して任せられる実績」を持つ退職代行となっています。
料金に関しても、パートやアルバイトの方の利用は19,800円と、業界でもかなりリーズナブルです。正社員の利用は少し費用がかかるものの、業界の相場に比べると高いというほどではありません。
女性特有のお悩みに関しても親身に対応してくれるため、女性の方で退職代行の利用を考えている場合の『第一候補』と言えるサービスです。
ただし「有給休暇や残業代などの交渉」には対応していないので、この点だけは注意しましょう。
| 料金 | ・パート・アルバイト:19,800円 ・正社員:29,800円 |
| 特徴 | ・創業16年、女性退職代行サービスNo.1 ・顧客満足度98.7% ・完全無料の転職サポートあり ・退職率100% ・JRAA(日本退職代行協会)の特級認定 |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 不可 |
| こんな人におすすめ | ・女性の方 ・リーズナブルな料金で手厚いサポートを受けたい方 ・安心して任せられる退職代行をお探しの方 |
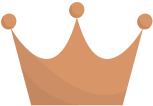 【3位】退職のススメ
【3位】退職のススメ
☆再就職サポートが手厚い上に、「実質0円」で退職可能

退職のススメは、同サービスが提供する再就職サポートを利用して転職に成功した場合、退職代行の料金は全額キャッシュバックされます。
つまり、「実質0円」で退職代行を利用できるのです。
このようなサポートを見ると「適当な会社を斡旋されるのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、再就職サポートを使うと、以降は永久無料で退職代行を依頼できるようになっています。
数ある退職代行サービスの中でも「再就職」へのサポートが手厚いのが特徴です。退職した後のことが不安という方におススメの退職代行と言えるでしょう。
| 料金 | 25,000円 |
| 特徴 | ・『実質0円』再就職サポート利用で全額キャッシュバック ・業界No.1!再就職支援実績10,000件以上 ・業界大手の退職代行サービスとしては最安値 ・退職率100% |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 可能 |
| こんな人におすすめ | ・退職代行を「無料」で利用したい方 ・退職だけでなく、再就職までサポートして欲しい方 |
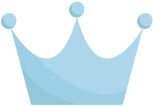 【4位】退職代行SARABA
【4位】退職代行SARABA
☆交渉が可能な退職代行サービスの最安値

退職代行SARABAは、労働組合が退職代行を行ってくれる退職代行サービスです。
労働組合法によって、企業は労働組合からの交渉を拒むことはできません。そのため、SARABAに依頼すると、退職代行はもちろん、残業代や有給といった「交渉」も行うことができます。
また、相談回数が24時間いつでも無制限に利用できるので、退職に対しての疑問や不安もしっかりフォローしてくれますよ。
退職後の転職サポートも無料で行ってくれるので、次の職場探しまで安心して任せることができます。
退職を考えるにあたってあると嬉しいサポートが揃っている上に、相場より安価に利用できるので、SARABAはコスパの良い退職代行サービスです。
| 料金 | 25,000円 |
| 特徴 | ・無料転職サポート付き ・24時間対応、相談回数無制限 ・行政書士監修の退職届がプレゼントされる ・成功率98%の有休消化サポート |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 可能 |
| こんな人におすすめ | ・安い料金で交渉ができる退職代行をお探しの方 ・退職後の転職活動が不安な方 ・料金とサービスのコスパが良い退職代行をお探しの方 |
[jin-rank5]【5位】退職代行ニコイチ
☆3万人以上の退職実績(退職数業界No.1)

退職代行ニコイチは、業界No.1の退職数を誇る退職代行サービスの先駆け的存在です。
多くの利用者がいるにもかかわらず、これまで一度もトラブル・クレームがないことからも、いかに誠実に退職代行を行ってくれるかが分かりますね。
その理由の一端は、弁護士が監修していることにあります。退職代行業者の中には「違法」な手続きを行なっている業者もあり、そのような業者に依頼をしてしまうと、退職自体が無効になってしまうケースも。
その点、ニコイチは合法的に退職代行を行なってくれるので、確実に退職をすることができますよ。
ただし、あくまで弁護士が「監修」しているだけであり、弁護士が直接対応してくれるわけではないので、有給や残業代といった交渉は行えません。
交渉は必要ないから、とにかく「絶対確実にトラブルなく退職したい」という方は、ニコイチを利用しましょう。
| 料金 | 27,000円 |
| 特徴 | ・3万人以上の退職実績(業界No.1) ・退職率100% ・弁護士監修だから安心安全に退職できる ・無料で退職届のテンプレートをもらえる ・無料の転職サポート付き |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 不可 |
| こんな人におすすめ | ・実績があり、信頼できる退職代行を使いたい方 ・他の退職代行サービスを利用して失敗した方 ・「絶対に」トラブルに巻き込まれたくない方 |











































