会社の経営陣として働く取締役。一見すると響きがよく、周りからは羨ましがられることもあるかもしれませんが、ストレスも溜まる大変な仕事ですよね。
取締役を辞任したいと考えるひともいることでしょう。取締役はいつでも辞任可能ですが、社員や代表取締役が辞任する場合とは手続きが若干異なります。
今回は、取締役が辞任した際にどんな手続きが必要なのか、辞任するに当たり事前に確認しておくべき項目などを紹介していきます。
取締役が辞任する際に必要な手続き
まずはじめに、取締役が辞任するにあたり、必要な手続きを確認していきましょう。
- 辞任の意思表示
- 登記申請書類の作成
- 変更登記申請を行う
辞任の意思表示
まずは、辞任の意思表示を確実に行いましょう。代表取締役を含む取締役は、会社とは委任関係にあるため自分の望んだタイミングで辞任をすることができます。
辞任することの意思表示は口頭でもできますが、書面として残るように辞任届を準備しましょう。口頭の場合、後々トラブルになる可能性もあるため、書面を用意しておく方が安心です。
登記申請書類の作成
辞任の意思表示を確認したら、今度は登記申請書類の作成を行います。法務局にて変更登記申請を行う必要があると覚えておいてください。
変更登記申請を行う
代表取締役や取締役の場合、社員とは違い氏名は登記事項となっているため、辞任などに伴い取締役が変わった場合には、登記簿謄本の内容を変更しなければなりません。
変更登記申請は取締役が辞任してから、基本的に2週間以内に手続きをする必要があります。書類の準備は迅速に行いましょう。
変更登記申請は取締役が辞任してから2週間以内に手続きを!
先ほども登場した「変更登記申請」ですが、取締役が辞任してから2週間以内に手続きをするのが一般的です。
2週間を過ぎてからでもできますが、あまりに遅くなってしまうと追加で料金を徴収されることもあるため、出来るだけ早めに終わらせてしまいましょう。
ちなみにですが、取締役などは定款にて人数が基本的に定められているため欠員を出すことはできません。取締役が4人のところを、1人辞任したまま変更登記申請はできないということです。
ということは、取締役が辞任をしたら、後任の取締役を2週間以内に決める必要があるということになるので、覚えておきましょう。
第三者に対して「辞任した」と公表できない
変更登記申請に関してですが、変更登記申請をしていなければ、第三者に対して「自分はこの会社の取締役を辞任した」と公表することができません。
厳密には、公表することはできても法的効力がないため、公表したところで意味がないのです。
例えば他社からの引き抜き等で、現在取締役を勤めている会社を辞めたとしても、変更登記申請が完了していない状態では、まだ辞任したことにはなりません。
辞任届を提出して受理されたとしても、変更登記申請が完了するまでは外部に公表しないほうがいいでしょう。辞任届の書き方については以下の記事でも紹介しているので、併せてご覧ください。https://executivenavi.com/archives/12
取締役辞任の手続きに当たり、取締役会について再度確認しよう
取締役会を設置している会社の場合には、取締役の最低人数を下回ることがないように注意しましょう。
辞任等により取締役の人数が3人以下になってしまうと、新たな取締役を選任するまでは、変更登記ができません。
ちなみにですが、取締役会を設置している会社の取締役の人数は最低でも「3人」と決められているため、仮に取締役が辞任して取締役の人数が2人となったら、取締役会を継続して設置しておくことはできません。
後任を選ぶか、取締役会を廃止するかを考えましょう。手続きの面を考えると、実はこの場合取締役会を廃止した方が賢い選択と言えるかもしれません。
取締役辞任の手続きに当たり、定款を確認しよう
取締役が辞任するに当たり、定款の内容を確認しておきましょう。1つ前の章で取締役会について再確認をしていただきましたが、定款の内容も重要になってきます。
定款で取締役の人数を規定している場合には、その規定の人数を下回ることがないように注意しなければなりません。
代表取締役の場合には、定款に記載されている内容によって手続きが大きく異なるため注意が必要です。代表取締役を務めていない取締役の場合には、定款に人数が規定されているかどうか等をチェックしてください。
取締役の辞任に当たり、株主総会の開催は必要なし
取締役の「辞任」に関しては、株主総会の開催は必要ありません。株主総会が必要だと思っている人も多くいますが、取締役の辞任の場合には、株主総会は開催しなくても大丈夫です。
会社が自発的に株主総会を開催し、「取締役が辞任した」旨を伝える分には構いません。しかしながら、取締役の辞任にあたり株主総会の開催義務はないわけです。
ただし、代表取締役の場合には株主総会の決議によって辞任を承諾してもらう必要がある場合もあります。
代表取締役の選定方法によって株主総会の承諾が必要かどうかも異なりますので、代表取締役の辞任手続きについてもチェックしておいてください。
取締役でも代表取締役の場合には注意
取締役とは言っても、「代表取締役」も務めている場合には辞任の際には注意が必要です。
代表取締役は、選定方法や定款に記載されている内容によって辞任できるかどうかや、代表取締役と取締役の2つの地位から辞任できるかどうかも、変わってきます。
また、代表取締役だけを辞めるつもりでも、辞任届の書き方や手続きによっては代表取締役も取締役の地位も失う場合があるので注意してください。
代表取締役の辞任手続きに関しては、以下の記事で詳しく触れているので併せてご覧ください。

取締役辞任の手続きに当たり、後任を決めよう
取締役が辞任をしたら、変更登記申請を行うことを考えて、後任を決めておきましょう。後任が決まるまでは、辞任届を提出したとしても実質的にはまだ取締役としての権利と義務が残ります。
取締役会を設置している会社の場合
ちなみにですが、取締役会を設置している会社は後任を決めなくてもいい場合があります。
取締役会を設置するためには、最低でも「3人」の取締役が必要となります。取締役が3人を下回った場合には、取締役会を廃止することも可能です。
取締役会を廃止すれば、取締役の人数は2人でも構わないので、後任を選定する必要がなくなります。
取締役が辞任する際に損害賠償の支払い手続きが必要な場合もある
取締役は会社を自分の望んだタイミングで辞任することができますが、場合によっては損害賠償を支払わなければならないケースがあります。
損害賠償を支払わなければならないケースというのは、会社が不利益を被るタイミング等で辞任をした場合です。
例えば会社の業務に「後任選び」等が入ってくることで、通常業務を行えなくなった場合などです。なお、やむを得ない理由で取締役を辞任した場合には損害賠償責任はありません。
いかなるタイミングで辞任したとしても、やむを得ない理由で辞任した場合には損害賠償の支払い責任はありません。損害賠償の支払い責任はケースバイケースだということを頭に入れておいてください。
まとめ
取締役が辞任した場合の手続きを紹介してきました。取締役は、代表取締役などと同様に、自分の望んだタイミングで辞任を表明することができます。
自分の望んだタイミングとはいえ、損害賠償責任も発生するケースがあるのでそう言った点は頭に入れておきましょう。
ただ、辞任をした後には会社としての手続きが発生することになります。面倒な業務が増えてしまいますし、手続きも代表取締役が辞任した時とは若干異なるため、きちんとした知識を蓄えておきましょう。
取締役の辞任が身近で起きたことがある人は少ないと思いますので、わからないポイントがあれば再度この記事を読み直してみてください。
本ページでは「とにかく安い値段で退職代行を使いたい」という方に向けて、数ある退職代行サービスの中から「依頼料の安い退職代行」をランキング形式でご紹介します。
とはいえ、いくら料金が安くても、退職できるとは限らないサービスは使いたくないですよね。
料金の安さはもちろんのこと、最低限しっかりと退職が実現できるだけの「サービスの質」も考慮したランキングとなっています。
「退職のために大きなお金は払いたくない。でも、しっかり退職までサポートしてもらえる退職代行サービスを利用したい」という方は、ぜひここで紹介している退職代行の利用を検討してみてください。
※以下に掲載する料金は全て「税込価格」です。
【格安で依頼可能】退職代行ランキング Top5
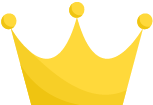 【1位】キャリアサンライズ
【1位】キャリアサンライズ
☆最も安い退職代行サービス

キャリアサンライズは、業界最安値でサービスを提供している退職代行サービスです。
退職代行の相場が3〜5万円なので、「他サービスの約半額」の料金で退職代行を依頼できるということになります。
ただし、この価格は「退職代行」に特化しているからこそできるものであり、残業代や有給に関する交渉などはサポート外となっています。
そのため、特に交渉をする予定はなく、ともかく安い料金で一刻も早く退職したいという方にお勧めのサービスです。
| 料金 | 15,000円 |
| 特徴 | ・業界最安値の退職代行サービス ・転職サポートのサービスもあり(別料金 |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 不可 |
| こんな人におすすめ | ・とにかく低価格で退職代行を依頼したい人 ・残業代などの交渉は考えていない人 |
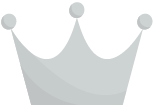 【2位】わたしNEXT
【2位】わたしNEXT
☆女性で退職代行の利用を考えている方の第一候補

わたしNEXTは、女性をメインターゲットとした退職代行サービスです。(男性も利用可能。)
日本退職代行協会の特急認定を受けてるほか、退職率100%、顧客満足度98.7%と「安心して任せられる実績」を持つ退職代行となっています。
料金に関しても、パートやアルバイトの方の利用は19,800円と、業界でもかなりリーズナブルです。正社員の利用は少し費用がかかるものの、業界の相場に比べると高いというほどではありません。
女性特有のお悩みに関しても親身に対応してくれるため、女性の方で退職代行の利用を考えている場合の『第一候補』と言えるサービスです。
ただし「有給休暇や残業代などの交渉」には対応していないので、この点だけは注意しましょう。
| 料金 | ・パート・アルバイト:19,800円 ・正社員:29,800円 |
| 特徴 | ・創業16年、女性退職代行サービスNo.1 ・顧客満足度98.7% ・完全無料の転職サポートあり ・退職率100% ・JRAA(日本退職代行協会)の特級認定 |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 不可 |
| こんな人におすすめ | ・女性の方 ・リーズナブルな料金で手厚いサポートを受けたい方 ・安心して任せられる退職代行をお探しの方 |
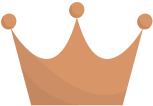 【3位】退職のススメ
【3位】退職のススメ
☆再就職サポートが手厚い上に、「実質0円」で退職可能

退職のススメは、同サービスが提供する再就職サポートを利用して転職に成功した場合、退職代行の料金は全額キャッシュバックされます。
つまり、「実質0円」で退職代行を利用できるのです。
このようなサポートを見ると「適当な会社を斡旋されるのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、再就職サポートを使うと、以降は永久無料で退職代行を依頼できるようになっています。
数ある退職代行サービスの中でも「再就職」へのサポートが手厚いのが特徴です。退職した後のことが不安という方におススメの退職代行と言えるでしょう。
| 料金 | 25,000円 |
| 特徴 | ・『実質0円』再就職サポート利用で全額キャッシュバック ・業界No.1!再就職支援実績10,000件以上 ・業界大手の退職代行サービスとしては最安値 ・退職率100% |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 可能 |
| こんな人におすすめ | ・退職代行を「無料」で利用したい方 ・退職だけでなく、再就職までサポートして欲しい方 |
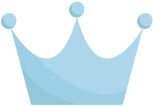 【4位】退職代行SARABA
【4位】退職代行SARABA
☆交渉が可能な退職代行サービスの最安値

退職代行SARABAは、労働組合が退職代行を行ってくれる退職代行サービスです。
労働組合法によって、企業は労働組合からの交渉を拒むことはできません。そのため、SARABAに依頼すると、退職代行はもちろん、残業代や有給といった「交渉」も行うことができます。
また、相談回数が24時間いつでも無制限に利用できるので、退職に対しての疑問や不安もしっかりフォローしてくれますよ。
退職後の転職サポートも無料で行ってくれるので、次の職場探しまで安心して任せることができます。
退職を考えるにあたってあると嬉しいサポートが揃っている上に、相場より安価に利用できるので、SARABAはコスパの良い退職代行サービスです。
| 料金 | 25,000円 |
| 特徴 | ・無料転職サポート付き ・24時間対応、相談回数無制限 ・行政書士監修の退職届がプレゼントされる ・成功率98%の有休消化サポート |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 可能 |
| こんな人におすすめ | ・安い料金で交渉ができる退職代行をお探しの方 ・退職後の転職活動が不安な方 ・料金とサービスのコスパが良い退職代行をお探しの方 |
[jin-rank5]【5位】退職代行ニコイチ
☆3万人以上の退職実績(退職数業界No.1)

退職代行ニコイチは、業界No.1の退職数を誇る退職代行サービスの先駆け的存在です。
多くの利用者がいるにもかかわらず、これまで一度もトラブル・クレームがないことからも、いかに誠実に退職代行を行ってくれるかが分かりますね。
その理由の一端は、弁護士が監修していることにあります。退職代行業者の中には「違法」な手続きを行なっている業者もあり、そのような業者に依頼をしてしまうと、退職自体が無効になってしまうケースも。
その点、ニコイチは合法的に退職代行を行なってくれるので、確実に退職をすることができますよ。
ただし、あくまで弁護士が「監修」しているだけであり、弁護士が直接対応してくれるわけではないので、有給や残業代といった交渉は行えません。
交渉は必要ないから、とにかく「絶対確実にトラブルなく退職したい」という方は、ニコイチを利用しましょう。
| 料金 | 27,000円 |
| 特徴 | ・3万人以上の退職実績(業界No.1) ・退職率100% ・弁護士監修だから安心安全に退職できる ・無料で退職届のテンプレートをもらえる ・無料の転職サポート付き |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 不可 |
| こんな人におすすめ | ・実績があり、信頼できる退職代行を使いたい方 ・他の退職代行サービスを利用して失敗した方 ・「絶対に」トラブルに巻き込まれたくない方 |












































