退職する際に使う辞表や退職届、退職願。どれも聞いたことのある書類ですが、どういった違いがあって、自分はどれを使ったらいいのか迷ってしまいますよね。
そこで、この記事では、辞表・退職届・退職願の違いや書き方などを紹介していきます。辞表などの受け取りを拒否されてしまった場合の対処法についても触れているので参考にしてくださいね。
(トップ画像出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84-%E6%9C%8D-%E7%94%B7-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-4165752/)
辞表はどんな人が使うもの?
 https://pixabay.com/ja/illustrations/%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF-%E6%9D%AD-%E8%B3%AA%E5%95%8F-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%AB-2492009/
https://pixabay.com/ja/illustrations/%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF-%E6%9D%AD-%E8%B3%AA%E5%95%8F-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%AB-2492009/辞表は、経営者や会社の運営に関わっている役員クラスの人、公務員の人が利用します。それ以外の人は退職届や退職願を使います。
ドラマなどで辞表を机に叩きつけるシーンがあるため、「退職=辞表」というイメージがある人もいるかもしれませんが、ほとんどの人は辞表を使う必要はありません。
間違えて辞表を使ってしまうと突き返されてしまうため、注意してください。次章では、退職届について紹介していきます。
辞表を使う必要のない人は退職届を使う
 https://www.pakutaso.com/20150711204post-1.html
https://www.pakutaso.com/20150711204post-1.html退職届は、公務員や役員以外の人が会社を辞める際に利用する書類です。
労働者と会社は労働契約で労働力と給与を交換することを取り決めていますが、退職届は、「この労働契約を終わりにします」と会社に宣言する意味合いがあります。
退職届を提出した後は、原則、退職を撤回することができません。そのため、退職する意志が固いときに利用するようにしましょう。
もし退職する意志がそこまで強くない場合は、退職願を利用してください。退職願については次章で紹介していきます。

退職願は退職届とどう違う?
 https://www.pakutaso.com/20190847233post-22775.html
https://www.pakutaso.com/20190847233post-22775.html前章で退職届を紹介しましたが、似たものとして退職願があります。退職願も辞表を使う必要のない人(公務員や役員以外の人)が退職する際に利用する書類です。
しかし、退職願と退職届は少し意味合いが違います。退職願は、労働者が会社に対して「労働契約を終わりにしてほしい」と願い出る意味合いを持っています。
退職願は退職届よりも退職する意志が強くない場合に利用しましょう。退職願は退職届と違って、提出した後も退職を撤回することができますよ。
次章以降では、辞表・退職届・退職願の書き方をそれぞれ解説していきます。
辞表の書き方
 https://pixabay.com/ja/photos/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E8%B3%AA%E5%95%8F-%E8%AA%B0-%E4%BD%95-3629655/#content
https://pixabay.com/ja/photos/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E8%B3%AA%E5%95%8F-%E8%AA%B0-%E4%BD%95-3629655/#contentここでは、辞表の書き方を紹介していきます。辞表を作成する時は、B5またはA4の用紙を使うようにしてください。辞表に入れ込むべき内容は以下の通りです。
- 「辞表」と書く
- 提出する日付
- 退職する旨・退職する日を書く
- 自分の役職と名前
- 捺印
- 会社名と代表取締役社長の名前
上記の内容を含んでいれば、書式には特に縛りはありません。ただ、会社で書式が定められている場合は、会社から辞表を受け取って、自分の名前を書き、捺印してくださいね。
手書きかパソコンでの作成かにかかわらず、縦書きが一般的です。縦書きは普段あまり利用しないため、書きにくいかもしれませんが、縦書きで書いておくほうが安心です。
以下に辞表のテンプレートを載せておきます。画面の見やすさを考慮して横書きにしていますが、実際に辞表を書く際は縦書きにしてくださいね。
 筆者作成
筆者作成退職届の書き方
 https://pixabay.com/ja/photos/%E6%9C%AC-%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%82%8A-%E5%AD%A6%E7%94%9F-%E8%B3%AA%E5%95%8F-4126482/#content
https://pixabay.com/ja/photos/%E6%9C%AC-%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%82%8A-%E5%AD%A6%E7%94%9F-%E8%B3%AA%E5%95%8F-4126482/#contentここでは、退職届の書き方を紹介していきます。退職届の用紙はB5またはA4を使用してください。下記に退職届に入れ込むべき内容をまとめてみました。
- タイトルに「退職届」と書く
- 提出する日付
- 退職する旨
- 退職する日
- 氏名と捺印
- 会社名と代表取締役社長の名前
上記の内容を入れ込んで、縦書きで書くのが一般的です。手書きのほうが良いとされていますが、パソコンで作成しても大丈夫です。
以下に退職届のテンプレートを載せておきます。画面の見やすさを考慮して横書きにしていますが、実際に書く際は縦書きで作成してください。
 筆者作成
筆者作成退職願の書き方
 https://pixabay.com/ja/photos/%E8%B3%AA%E5%95%8F-%E7%96%91%E5%95%8F%E7%AC%A6-%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%B3-3838906/#content
https://pixabay.com/ja/photos/%E8%B3%AA%E5%95%8F-%E7%96%91%E5%95%8F%E7%AC%A6-%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%B3-3838906/#contentここでは、退職願の書き方を紹介していきます。退職願を書く用紙は、B5やA4サイズを使用してください。下記に退職願に書く内容をまとめてみたので、確認しておきましょう。
- タイトルに「退職願」と書く
- 提出する日付
- 退職を願い出る文言
- 退職したい日
- 自分の名前と捺印
- 会社名と代表取締役社長の名前
手書きかパソコンで作成したかにかかわらず、縦書きにするのが一般的です。以下に退職願のテンプレートを載せておきます。
見やすさを考慮して横書きにしていますが、実際に作成する時は縦書きにしてくださいね。
 筆者作成
筆者作成封筒の書き方
 https://www.pakutaso.com/20140200036post-3800.html
https://www.pakutaso.com/20140200036post-3800.htmlここでは、辞表・退職届・退職願を入れる封筒の書き方を紹介していきます。使う封筒は白地で中身が透けて見えないものを使うようにしてください。
封筒の大きさは中に入れる書類の大きさで決めます。書類がB5サイズであれば長形4号、A4サイズであれば長形3号を使うと丁度よいですよ。
書類は三つ折りにするのがマナーで、最初に下から折り曲げ、その後上から折り重ねます。また、入れる向きも決まりがあり、封筒の裏側から見て書類の右上が右上に来るように封筒へ入れ込みます。
封筒の表側の真ん中に中に入れた書類の種類を書いてください。裏側は自分の所属している課と氏名を書き込んでおきましょう。宛名は書かないのが基本です。
封筒の封はしなくて良いのですが、ノリが元からついている封筒の場合は見栄えの関係上、封をします。封をするときには「〆」を書くようにしてください。
 筆者作成
筆者作成辞表・退職届・退職願を提出するタイミング
 https://pixabay.com/ja/photos/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%87%90%E4%B8%AD%E6%99%82%E8%A8%88-%E9%81%8B%E5%8B%95-3179167/
https://pixabay.com/ja/photos/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%87%90%E4%B8%AD%E6%99%82%E8%A8%88-%E9%81%8B%E5%8B%95-3179167/退職の意志を伝える辞表・退職届・退職願は、退職したい日の1か月以上前に退出するようにしてください。
法律的には14日以上前に提出すれば良いとされていますが、仕事の引継ぎや取引先への挨拶を考えると1か月以上前に提出するほうが無難です。
また、就業規則で「退職の意志は〇日前までに伝えること」と規定されている場合は、その就業規則に従ってくださいね。
次章では、辞表・退職届・退職願の受け取りを拒否されてしまった場合の対処法について紹介していきます。
辞表・退職届・退職願の受け取りを拒否されてしまった場合
 https://pixabay.com/ja/illustrations/%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%88-%E8%B2%A0-%E6%8C%87-%E6%89%8B-%E7%B6%AD%E6%8C%81-1532826/
https://pixabay.com/ja/illustrations/%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%88-%E8%B2%A0-%E6%8C%87-%E6%89%8B-%E7%B6%AD%E6%8C%81-1532826/辞表・退職届・退職願の受け取りを拒否されてしまったら、まずは会社の人事部へ相談しましょう。上司は部下が辞めると上からの評価が落ちたり、自分の仕事が増えたりするので、受け取りを拒否することがあります。
人事部であればそういった利害関係がないため、すんなり受け入れてくれる可能性もあります。もし、万が一、自分が人事部であったり、人事部が受け取りを拒否してくる場合は労働基準監督署に相談してください。
労働基準監督署に相談すれば、辞表などの受け取りを拒否したことに関して、会社へ指導を行ってくれますよ。

辞表・退職届・退職願の違い まとめ
辞表・退職届・退職願の違いや書き方について紹介してきました。それぞれ違いがあり、自分の立場や状況に応じたものを使うことが大切です。
書き方については細かい書式は決まっていませんが、記事で紹介した内容やテンプレートを参考にしてもらえれば大丈夫です。
ただし、会社によってはその会社専用の辞表・退職届・退職願がある場合もあります。そういった時は、会社から書類をもらい、自分の氏名などを書くだけで完成しますよ。
この記事を参考にして、正しく書類を提出して円満に退職してくださいね。
本ページでは「とにかく安い値段で退職代行を使いたい」という方に向けて、数ある退職代行サービスの中から「依頼料の安い退職代行」をランキング形式でご紹介します。
とはいえ、いくら料金が安くても、退職できるとは限らないサービスは使いたくないですよね。
料金の安さはもちろんのこと、最低限しっかりと退職が実現できるだけの「サービスの質」も考慮したランキングとなっています。
「退職のために大きなお金は払いたくない。でも、しっかり退職までサポートしてもらえる退職代行サービスを利用したい」という方は、ぜひここで紹介している退職代行の利用を検討してみてください。
※以下に掲載する料金は全て「税込価格」です。
【格安で依頼可能】退職代行ランキング Top5
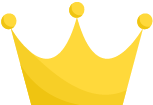 【1位】キャリアサンライズ
【1位】キャリアサンライズ
☆最も安い退職代行サービス

キャリアサンライズは、業界最安値でサービスを提供している退職代行サービスです。
退職代行の相場が3〜5万円なので、「他サービスの約半額」の料金で退職代行を依頼できるということになります。
ただし、この価格は「退職代行」に特化しているからこそできるものであり、残業代や有給に関する交渉などはサポート外となっています。
そのため、特に交渉をする予定はなく、ともかく安い料金で一刻も早く退職したいという方にお勧めのサービスです。
| 料金 | 15,000円 |
| 特徴 | ・業界最安値の退職代行サービス ・転職サポートのサービスもあり(別料金 |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 不可 |
| こんな人におすすめ | ・とにかく低価格で退職代行を依頼したい人 ・残業代などの交渉は考えていない人 |
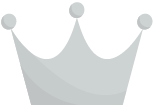 【2位】わたしNEXT
【2位】わたしNEXT
☆女性で退職代行の利用を考えている方の第一候補

わたしNEXTは、女性をメインターゲットとした退職代行サービスです。(男性も利用可能。)
日本退職代行協会の特急認定を受けてるほか、退職率100%、顧客満足度98.7%と「安心して任せられる実績」を持つ退職代行となっています。
料金に関しても、パートやアルバイトの方の利用は19,800円と、業界でもかなりリーズナブルです。正社員の利用は少し費用がかかるものの、業界の相場に比べると高いというほどではありません。
女性特有のお悩みに関しても親身に対応してくれるため、女性の方で退職代行の利用を考えている場合の『第一候補』と言えるサービスです。
ただし「有給休暇や残業代などの交渉」には対応していないので、この点だけは注意しましょう。
| 料金 | ・パート・アルバイト:19,800円 ・正社員:29,800円 |
| 特徴 | ・創業16年、女性退職代行サービスNo.1 ・顧客満足度98.7% ・完全無料の転職サポートあり ・退職率100% ・JRAA(日本退職代行協会)の特級認定 |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 不可 |
| こんな人におすすめ | ・女性の方 ・リーズナブルな料金で手厚いサポートを受けたい方 ・安心して任せられる退職代行をお探しの方 |
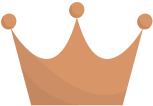 【3位】退職のススメ
【3位】退職のススメ
☆再就職サポートが手厚い上に、「実質0円」で退職可能

退職のススメは、同サービスが提供する再就職サポートを利用して転職に成功した場合、退職代行の料金は全額キャッシュバックされます。
つまり、「実質0円」で退職代行を利用できるのです。
このようなサポートを見ると「適当な会社を斡旋されるのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、再就職サポートを使うと、以降は永久無料で退職代行を依頼できるようになっています。
数ある退職代行サービスの中でも「再就職」へのサポートが手厚いのが特徴です。退職した後のことが不安という方におススメの退職代行と言えるでしょう。
| 料金 | 25,000円 |
| 特徴 | ・『実質0円』再就職サポート利用で全額キャッシュバック ・業界No.1!再就職支援実績10,000件以上 ・業界大手の退職代行サービスとしては最安値 ・退職率100% |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 可能 |
| こんな人におすすめ | ・退職代行を「無料」で利用したい方 ・退職だけでなく、再就職までサポートして欲しい方 |
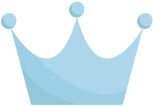 【4位】退職代行SARABA
【4位】退職代行SARABA
☆交渉が可能な退職代行サービスの最安値

退職代行SARABAは、労働組合が退職代行を行ってくれる退職代行サービスです。
労働組合法によって、企業は労働組合からの交渉を拒むことはできません。そのため、SARABAに依頼すると、退職代行はもちろん、残業代や有給といった「交渉」も行うことができます。
また、相談回数が24時間いつでも無制限に利用できるので、退職に対しての疑問や不安もしっかりフォローしてくれますよ。
退職後の転職サポートも無料で行ってくれるので、次の職場探しまで安心して任せることができます。
退職を考えるにあたってあると嬉しいサポートが揃っている上に、相場より安価に利用できるので、SARABAはコスパの良い退職代行サービスです。
| 料金 | 25,000円 |
| 特徴 | ・無料転職サポート付き ・24時間対応、相談回数無制限 ・行政書士監修の退職届がプレゼントされる ・成功率98%の有休消化サポート |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 可能 |
| こんな人におすすめ | ・安い料金で交渉ができる退職代行をお探しの方 ・退職後の転職活動が不安な方 ・料金とサービスのコスパが良い退職代行をお探しの方 |
[jin-rank5]【5位】退職代行ニコイチ
☆3万人以上の退職実績(退職数業界No.1)

退職代行ニコイチは、業界No.1の退職数を誇る退職代行サービスの先駆け的存在です。
多くの利用者がいるにもかかわらず、これまで一度もトラブル・クレームがないことからも、いかに誠実に退職代行を行ってくれるかが分かりますね。
その理由の一端は、弁護士が監修していることにあります。退職代行業者の中には「違法」な手続きを行なっている業者もあり、そのような業者に依頼をしてしまうと、退職自体が無効になってしまうケースも。
その点、ニコイチは合法的に退職代行を行なってくれるので、確実に退職をすることができますよ。
ただし、あくまで弁護士が「監修」しているだけであり、弁護士が直接対応してくれるわけではないので、有給や残業代といった交渉は行えません。
交渉は必要ないから、とにかく「絶対確実にトラブルなく退職したい」という方は、ニコイチを利用しましょう。
| 料金 | 27,000円 |
| 特徴 | ・3万人以上の退職実績(業界No.1) ・退職率100% ・弁護士監修だから安心安全に退職できる ・無料で退職届のテンプレートをもらえる ・無料の転職サポート付き |
| 返金保証 | あり |
| 交渉の可否 | 不可 |
| こんな人におすすめ | ・実績があり、信頼できる退職代行を使いたい方 ・他の退職代行サービスを利用して失敗した方 ・「絶対に」トラブルに巻き込まれたくない方 |













































